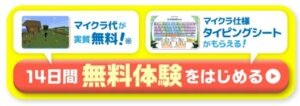「子どもにプログラミングを学ばせたいけれど、ちゃんと身についているのか分からない…」
んな保護者の方に注目されているのが、デジタネで受けられる「プログラミング能力検定(プロ検)」です。
この検定は、小学生でもチャレンジしやすく、しかも自宅からオンライン受験が可能。
さらに、学習教材と連動しているため、日々の学習がそのまま対策に直結します。
この記事ではプロ検の内容・レベル別の難易度・オンライン受験の流れ・保護者のサポートポイントまで、詳しく解説します。
プログラミング能力検定ってどんな検定
「プログラミング能力検定(通称:プロ検)」は、全国の小中高生を対象にした、プログラミングの理解力と論理的思考力を測定する検定試験です。
主催しているのは「一般社団法人プログラミング能力検定協会」で、全国のプログラミング教室やオンラインスクール、学校教育の現場でも活用されており、徐々にその認知度と信頼性が高まっています。
プロ検では、プログラミング言語そのものの技術だけではなく、「順次処理」「繰り返し」「条件分岐」「変数」などの基礎的な概念をどれだけ理解しているかが問われます。
つまり、単にコードを書けるかではなく、論理的に考えて正しく組み立てられる力があるかどうかを測るのです。
また、プロ検にはレベル1〜6までの段階が設けられており、子どもの習熟度や年齢に応じて適切なレベルに挑戦できます。
たとえば、小学校低〜中学年であれば「ビジュアル言語(Scratchなど)」を使ってLevel1〜2に取り組むことができますし、より進んだ子どもや中高生には「テキスト言語(Python、JavaScriptなど)」での受験が推奨されます。
デジタネで受けられる「オンライン受験」の特徴
プロ検は、一般的には指定された会場に足を運んで受験するスタイルが主流ですが、デジタネの会員であれば自宅のパソコンからオンラインで受験することができます。
これは、忙しい家庭や、試験会場までの距離が遠い家庭にとって、非常に大きなメリットです。
オンライン受験のメリット
- 送迎や移動の必要なし:自宅のリビングや子ども部屋で、落ち着いて試験を受けられます。
- 慣れた環境で実力を発揮できる:試験会場の緊張感が苦手な子どもでも、普段の環境で集中しやすい。
- 学習から受験までが一本化:デジタネのカリキュラムがそのままプロ検に準拠しているため、学びと試験が直結。
- 柔軟な日程調整が可能:予約制でスケジュールも柔軟に対応可能(※公式スケジュールは要確認)。
このように、オンライン受験は子どもにとっての心理的ハードルを下げるだけでなく、保護者の負担軽減にもつながる選択肢です。
また、デジタネでは「オンライン受験サポート体制」も充実しており、事前準備のチェックリストやFAQも公式に公開されています。
ただし、オンライン受験には一定の条件があります。
- パソコン(タブレット不可)
- Google Chromeなどの対応ブラウザ
- 安定したインターネット回線
- 試験中に保護者が手助けをしない環境の確保
これらを満たさない場合、受験そのものができなかったり、無効になることもあるため、事前に環境チェックをしておくことが重要です。
また、試験中は時間制限(30分〜60分)があり、回答を途中で止めたり、ブラウザを閉じると無効になるケースもあるため、お子さんが緊張せずスムーズに操作できるよう、練習環境を用意してあげると安心です。
レベル別にわかる!プログラミング能力検定の出題内容と対象年齢の目安
「プログラミング能力検定には6段階のレベルがあるけど、うちの子はどこから始めればいいの?」
そんな疑問に応えるために、この章では各レベルの出題範囲・使用言語・難易度・対象年齢の目安を詳しく解説します。
プロ検は、Level1〜4はビジュアル言語(Scratchなど)対応、Level5〜6はテキスト言語(Pythonなど)対応となっており、段階的にスキルアップできる構成です。
Level1〜4の難易度と内容(ビジュアル言語対応)
使用言語:ビジュアル型(主にScratchなど)
小学生が最初に挑戦しやすいのがこのレベル帯です。
コードを直接入力するのではなく、ブロックを組み合わせてプログラムを作る方式のため、パソコン操作に慣れていれば低学年からでも無理なく取り組めます。
| レベル | 出題内容 | 対象の目安 |
|---|---|---|
| Level1 | 順次処理(命令を順に実行)入力と出力 | 小1〜小3程度初学者向け |
| Level2 | 繰り返し(ループ)、条件分岐の基礎 | 小2〜小4程度 |
| Level3 | 複数条件分岐、変数の利用 | 小4〜小6程度 |
| Level4 | リスト(配列)、関数の考え方 | 小6〜中1程度Scratch経験者向け |
このレベル帯では、Scratchを使って遊び感覚で取り組んでいたお子さんが、徐々に「考えて組み立てる力」を試されるようになります。
単なる作業ではなく、「なぜそうなるのか?」を理解する力が求められ、自走力を育む第一歩にもなるフェーズです。
Level5〜6の難易度と内容(テキスト言語対応)
使用言語:テキスト型(Python/JavaScript/Java)
| レベル | 出題内容 | 対象の目安 |
|---|---|---|
| Level5 | 関数、変数のスコープ、複雑な条件分岐、ループ | 中学生〜高校生初級 |
| Level6 | 複数ファイルの扱い、クラス、オブジェクト指向の基礎 | 高校生〜大学生初級 |
この段階になると、ただの習い事や趣味というよりも、将来的なITスキルの育成・進学対策にもつながるレベル感です。
保護者としては、「テキストに進むべきか」「Scratchのままでいいか」悩むこともあると思いますが、焦らずにビジュアル言語での理解が十分に深まってからで問題ありません。
小学生にはどのレベルが最適?
一般的には、小学生にはLevel1〜3が最も取り組みやすいレベルとされています。
特に、Scratchなどで遊んだことがある子どもなら、Level2や3も十分にチャレンジ可能です。
レベル選びの目安(保護者向け)
- 初めてプログラミングに触れる子 → Level1からスタート
- Scratch経験が半年以上ある子 → Level2〜3に挑戦
- 算数やパズルが得意で論理的思考が好きな子 → Level3〜4も視野に
また、プログラミング能力検定の過去問や練習問題をデジタネで確認できるので、事前にどのくらいの問題に取り組めるかを見て、レベルを選ぶのが安心です。
さらにデジタネでは、定期的な模擬試験やレベル診断などのサポートも提供されているため、「我が子に合ったレベルがわからない」という場合でも、学習の中で自然に適切なレベルを見極められる仕組みがあります。
デジタネの教材がプログラミング能力検定対策に強い理由
子どもに検定を受けさせるうえで、「ちゃんと合格できるだけの教材やサポートがあるのか?」は保護者が最も気になるポイントです。
その点、デジタネはプログラミング能力検定と連動したカリキュラム設計、充実した演習環境、やる気を引き出す仕組みが揃っており、まさにプログラミング能力検定対策に最適なオンライン教材といえます。
検定と連動したカリキュラム
デジタネのカリキュラムは、プロ検の出題範囲に完全準拠して作られています。
「順次処理」「条件分岐」「繰り返し」「変数」「関数」など、検定で問われる内容が段階的に登場し、学習の中で自然と合格に必要な力が身につく構成になっています。
特に小学生向けのビジュアル言語(Scratch)コースでは、プロ検Level1〜4の範囲にピッタリ対応しているため、日々の学習をこなしていけば、受験前に特別な対策をしなくても基本的な力がつきます。
また、各レッスンでは「なぜこうなるのか」を丁寧に解説してくれるため、暗記ではなく理解で学べる点も大きなメリットです。
検定に合格するだけでなく、「将来につながる本当の思考力」を育む設計がなされています。
演習・模試・弱点補強機能が豊富
ただ学ぶだけでなく、実践的な問題演習ができる点もデジタネの強みです。
プログラミング能力検定形式の模擬問題が定期的に配信され、実際の試験に近い形式に慣れることができます。
苦手な単元はAIが自動で分析し、「弱点補強ドリル」として再学習できる仕組みがあるため、取りこぼしがありません。
一定のステップが終わるごとに理解度チェックテストが用意されており、「分かったつもり」を防げます。
こうした演習中心の機能により、ただ映像を見て終わるような受け身の学習ではなく、自分の手で考え、作り、試し、修正するという“アクティブラーニング”が実現されています。
また、模試で一定以上の成績を出すと、合格の目安としての指標ももらえるため、保護者も「本番前にどれくらいの仕上がりか」を把握しやすいです。
モチベーションを高める仕組み
オンライン学習で意外と大切なのが、子どものやる気をいかに維持するかという点です。
デジタネでは、モチベーション維持にもさまざまな工夫がされています。
ポイント・バッジ制度:課題をクリアするとポイントが貯まり、バッジやキャラクターがもらえる「ごほうび要素」付き。
ランキング機能:他のユーザーとの進捗比較ができ、「負けたくない!」という気持ちがやる気に火をつけます。
音声・アニメーションによる解説:まるでゲームのような楽しさで、学びが苦にならない設計。
さらに、保護者用の管理画面では、子どもの学習時間・進捗・正答率などを一覧でチェックできるため、適切な声かけやサポートが可能です。
「今日はちょっと集中してるね」「昨日は苦手な問題をがんばったね」といった会話を通じて、家庭内でのコミュニケーションツールにもなるのがデジタネならではの魅力です。
このように、デジタネはただのプログラミング教材ではなく、プロ検合格を見据えた“トータル学習システム”です。
日々の学習がそのまま試験対策につながるからこそ、効率的に、無理なく、子どもの力を伸ばすことができます。
プログラミング能力検定受験までの流れと必要な準備【チェックリスト付き】
「プログラミング能力検定って申し込みが複雑そう…」「何を準備すればいいの?」
初めて受ける場合、こうした不安を感じる保護者も多いはずです。
このセクションでは、デジタネ経由でプロ検を受ける際の申し込み方法・費用・準備すべき機材や環境・当日の流れまでを、わかりやすく解説します。
申込方法・スケジュール・費用
- デジタネの有料プランに登録
- マイページから「プロ検オンライン受験」の申込ページにアクセス
- 希望するレベルと受験日程を選択
- 受験料を支払い(クレジットカード対応)
- 申し込み完了後、詳細メールが届く
スケジュールの目安
- 受験は毎月1〜2回程度実施(月によって変動あり)
- 申し込み締切は受験日の1週間前程度が目安
- 受験時間はレベルによって30〜60分程度
受験日は事前に公式スケジュールが公開されているため、習い事や予定と調整しながら申し込めるのがオンライン受験の利点です。
検定料(オンライン受験)
| レベル | 受験料(税込) |
|---|---|
| Level1 | 3,300円 |
| Level2 | 4,400円 |
| Level3 | 5,500円 |
| Level4 | 6,600円 |
| Level5 | 7,700円 |
| Level6 | 8,800円 |
必要な環境(PC・ブラウザ・ネットなど)
オンライン受験には、以下のような最低限の機材と環境が必須です。
事前にチェックしておくことで、当日のトラブルを防ぐことができます。
受験環境チェックリスト
- パソコン(Windows または Mac) ※タブレット・スマホは不可
- インターネット環境(安定したWi-Fiまたは有線LAN)
- ブラウザ:Google Chrome(最新版)
- キーボードとマウスの操作に慣れていること(特にLevel3以降)
- カメラとマイクは基本不要(ただし本人確認のため、保護者の付き添いが求められる場合あり)
- 静かな場所と集中できる時間の確保
これらを満たしていないと、受験ができなかったり、不正扱いで失格になるケースもあるため要注意です。
当日の流れと注意点
受験当日の基本的な流れ
- 受験開始時間の10〜15分前にはPCの前でスタンバイ
- デジタネのマイページから試験ページにアクセス
- ログイン後、案内に従って受験開始
- 制限時間内にすべての設問に回答(途中退出不可)
- 終了後、自動で採点が行われ、後日結果が通知される
注意点(保護者向け)
試験中の操作補助は禁止:操作ができる年齢か確認しておく
インターネットの安定性が重要:途中で切れると最悪失格になることも
兄弟・家族の生活音や話しかけもNG:静かな環境づくりを忘れずに
デジタネからは事前に「受験マニュアルPDF」も配布されるので、前日までに子どもと一緒に確認しておくと安心です。
プログラミング検定合格で得られる子どもの変化とは?
「子どもに検定を受けさせたら、どんなメリットがあるの?」これは多くの保護者が気になるポイントです。
プログラミング能力検定は、単なる“合格”という結果以上に、子どもの内面や学習姿勢にポジティブな変化をもたらしてくれる検定です。
「やる気」「自己肯定感」「次の目標」
プログラミング能力検定に合格することで、子どもにまず現れるのが「自信がついた」「次も頑張りたい!」という気持ちの変化です。
これは、大人が思っている以上に大きな効果があります。
成功体験が自己肯定感につながる
検定合格という「目に見える成果」は、子どもにとっての大きな成功体験になります。
特に小学生の場合、自分の努力が認められたり、周囲に褒められることで、「もっとやってみよう」「自分にもできるかも」という前向きな気持ちが自然と芽生えます。
「勉強=やらされるもの」だった子が、「勉強=自分の力になる」と実感できるようになることは、将来的な学習意欲の土台づくりにおいて非常に大切です。
次のステップに向けてのモチベーションアップ
合格証が届いたあと、子どもが自然に「次のレベルにも挑戦してみたい!」と言い出すケースも珍しくありません。
プログラミング能力検定のレベル構成がステップアップ式になっているため、「次の目標が設定しやすい」=モチベーションが維持しやすいという仕組みになっているのです。
さらに、検定に合格したことで「自分はプログラミングが得意なんだ」と思えるようになった子は、学校の情報科目やSTEM教育の場面でも積極性を見せるようになったという声もあります。
将来的に役立つスキルの可視化
プログラミング能力検定に合格することで得られるのは、学習意欲や自信だけではありません。
将来的に役立つ“スキルの証明”になるという点でも、大きな意味があります。
中学・高校での学びにつながる
プログラミング教育は、すでに小学校で必修化されており、今後は中学・高校でも「情報」科目として本格化していきます。
プログラミング能力検定で身につくアルゴリズムの理解、条件分岐、ループ処理などの考え方は、そうした情報教育の基礎として非常に有効です。
また、デジタネで学習している子どもたちは、単に操作方法だけでなく「なぜそうなるのか」を理解しているため、学校の授業でも理解が深まりやすくなります。
入試・資格としての活用も視野に
プログラミング能力検定は、現時点では大学入試の加点対象資格にはなっていませんが、将来的に「情報系スキルの証明」として活用される可能性が十分にあります。
実際、IT関連の高校や専門学校への入試時に、「プログラミング能力検定を保有しているか」が評価対象になる例も少しずつ増えてきています。
また、保護者の立場からしても、履歴として「〇〇レベルの検定に合格済み」と残ることで、学習の成果が目に見える形で記録として残るのは大きな安心感につながります。
このように、プログラミング能力検定に合格することは、ただの“スキルの証明”にとどまらず、子どもの内面の成長・学びの習慣化・将来への可能性を広げる機会にもなります。
「なんとなく学ばせているプログラミング」を、「目標を持って取り組む学び」へと昇華させてくれる。
それが、デジタネとプログラミング能力検定の大きな価値です。
デジタネでプロ検に挑戦してみよう!
プログラミングの力は、これからの社会を生き抜く子どもたちにとって欠かせないスキルの一つです。
その力を「見える形で証明できる」のが、プログラミング能力検定。
そして、そのプロ検の合格に向けて、確かな学習環境と実績を持つのが「デジタネ」です。
デジタネでは、プログラミング能力検定に対応したカリキュラムと演習機能、モチベーション維持の仕組みが整っており、学び→実践→合格という一連の流れを、子どもが自分のペースで進められるように設計されています。
「うちの子にできるかな?」と不安な方も大丈夫。
まずは一歩踏み出して、可能性を広げてみませんか?